


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| フォトでコラム| 今日もはやく帰りたい|
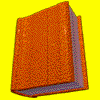 一度舞台にたったらやめられない
一度舞台にたったらやめられない
久々にページをめくる速度が速くなる痛快な本に出会った。くだらなさと真剣さとカブキの史実がいる乱れ、時間も空間も平気で超えてゆく。普通この手の迷宮物は作者のひとりよがりになるのだが、作者が遊んでる感じが伝わってきて、必死さもなく嫌味がありません。
そもそも時間軸は舞台ではカブキが演じられ、楽屋に迷い込む少年少女がいるのだが、その楽屋がどこでもドア状態になっているまか不思議な楽屋。ストーリーは読んでもらうとして、めちゃめちゃ気に入った部屋が、踊りの練習をしてる楽屋。なんとその迷宮の世界でどんな踊りをしてるかと思いきや、パソコンのマウスを持って踊ったり、殺虫剤を持って踊ってるんです。笑わせてもらいました。シティボーイズのライブでやりたいくらいです。カブキという伝統的ものをイメージしてるもんだから、その裏切り方は全くのギャグ。そしてその後に踊りに対する小林さんの考え方が展開されてゆくんですが、それもどこか真面目そうに出鱈目だよっと言ってる感じもあって、なかなかのインテリですね。
私も役者の端くれとして、この本は勉強になりましたね。一度舞台にたったらやめられないとはよく言いますが、人にみられる快感はどうやっても日常では得られない快感。そこから我を忘れる興奮状態に至れれば、もう麻薬をやっているようなもの。やめれませんね。それでもカブキのある超名人はスパッとやめたという。舞台上でああやれこうやれという「カブキの神」の声が聞こえなくなったというのだ。かっこいいじゃありませんか。確かに私にも神とは言わないまでも「ここでギャグ!」と聞こえて来る時がありますね。時々、その声はおおハズレの場合もあるのですが、何かに操られている感覚は舞台に立った人じゃないとわからんでしょうね。そして何かに操られて自由に演技をする役者を見た時、観客も興奮し、元気になって、同時代に生きてることに勇気がわくんでしょうか。
カブキ界には三奇と呼ばれる至宝があるそうで、その一つが初代団十郎が日本一の役者にになろうと成田山に捧げた「願文」だという。そこには男色、女色、酒を禁じて、ひたすらに神仏の加護を求めているという。役者は遊ばなきゃダメだと言われていることと正反対だ。私も生理的に男色は禁じているが、あとの二つはどうも。確か菊池寛の「藤十郎の恋」では女遊びが舞台で恐いほどのリアリズムとなって客に迫ったとありました。リアリズムか神がかりか、役者のあり方も奥が深いのですよ。この小説も混沌と秩序があり。どちらにも加担しない方法論は好きですね。生の舞台をみたいと思わせる素敵な小説でした。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '98年9月号掲載)


