


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| フォトでコラム| 今日もはやく帰りたい|
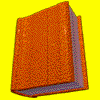 天才と呼ばれないようにしよう
天才と呼ばれないようにしよう
なんともスリリングな本であった。横山やすしさんにしろ、その周辺の実在の人物に対しても、小林信彦氏のその距離の置き方はペンの殺気みたいなものを感じる。
あとがきに「さまざまな意味で筆を抑制したが、しかし、真実を書かないわけにはいかない。疲れたのはこのバランスのためである」とある。ここにある真実とは小林氏の判断や意見のことで、事実より恐いものになっている。自分の立場や保身を考えていたら、書けなかっただろうし、相当に自分に自信がある方とお見受けする。笑いをする人に必要なアナーキーな部分を小林氏自身が持っている。
圧巻は小林氏がやすしの部屋に訪ねてみると高信太郎さんがいるくだり。冷静な描写は、爽快で悲しくも笑ってしまう。泥酔のコーシンがやすしになつき、やすしが親分のように振る舞う様子はやすしの人間的な弱さや孤独が浮き彫りになってゆく。この二人は立場がいつ逆転してもおかしくないとさえ感じさせる。とにかく「第十章 嗚咽 」、一言一言の会話の再現で、こんなにも人物が描けるとはおそれいりました。
私としても漫才ブームの端っこにいて、やすしさんを何度かお見かけした。あのビッチリ決めた髪型とテカテカの靴。どこからみても天才とは思えなかった。天才というより、野心家の水商売のおっさんというイメージ。やすきよの漫才にしても、漫才ブームの頃はおおトリで、責任感というか名人というレッテルでつらそうだなという印象しかない。つらいからお客に媚びるようなやすしさんを私としてはあまり笑えなかった。強烈な野心が外側に出て、枯れることを知らないパワーを人は天才と言ったのだろうか。
シティボーイズも大阪の難波花月に十日間出演したことがある。隣の楽屋で、やすしさんの怒鳴る声を聞いた。その日は団体客がいて超満員だったが、トリのやすきよが出る前に団体客が時間の都合で帰ってしまったのだ。やすしさんはマネージャーに怒っている。
「なんで、わしらを先にださんのや! 客はわしらを見に来とるんや!順番なんてどうでもいいやろうが!アホ!」。 確かに客はやすきよを見たかったに違いない。でも私がその地位にいても、他の芸人さんもいる。こうははっきりいい切れんだろうな。これがプロ意識なんだろうかと感心した。惰性のように毎日やってる舞台で客のことを考えられる。東京の演芸場では考えられない事だった。自分のおかれている立場を直感的にわかる人なんだろう。いや敏感すぎる人だったのかもしれない。そう思うと晩年のつらさが身にしみてくる、 私は立場をいつまでも認識しない人になって、天才と呼ばれないようにしよう。まあ誰も呼ぶ人はいないのでラッキー。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '98年5月号掲載)


