


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
“きのう読んだ本はこんな本”では、みなさまのご意見やご感想をお待ちしています。
メールのあて先はこちらまで。
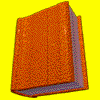 天才的英雄とはそうしたものだ
天才的英雄とはそうしたものだ
「蝶のように舞い、蜂のように刺す」この言葉とともに忘れがたいボクサー、モハメッド・アリ。対戦相手は定かではなくても試合ぶりは鮮明に思い出すことができる。リングにあがればエキサイトしてるのか冷静なのか、理解を超えた罵声を相手にあびせ、その段階でアリのすざまじい集中力に圧倒された。信じられない程の後ろへさがりながらのパンチの連打。あれだけ相手を軽蔑できるのだろうかというフットワークと彼の眼。そしてその眼は時には怯えているようにも見えた。その動作ひとつひとつが独創的で、白人に戦わされている黒人でなく、黒人こそ美しい、これからの時代を変えてゆく人種だと思わせた。まさに70年代の英雄だった。
この「モハメッド・アリの道」はそんなアリの生い立ちをつづった本かと思いきや、違った。引退後のアリの生活ぶりや考え方が紹介されてゆく。というより、この作者の半生が克明に書かれてゆく。「スポーツライターになるまでの道」と言っていいかも知れない。アリに憧れ、アリを追いかけ、どんどんアリの中にはいってゆく。アリの評価ににしても凄い。「彼がボクシング界の英雄でなかったとしても、必ずや何かの力が働いて、きっと彼を今世紀もっとも影響力をもつ人間のひとりにし、希望に満ちた、すばらしく、せつなく、美しい神話を最後には創りあげたはずだ」
ちょっと世界とレベルは違うが、天才巨人の長嶋だって、野球じゃなくとも人に影響を与え感動させてくれたに違いない。持って生まれた人を楽しませる力と集中力。そして二人に共通する無邪気さ。天才的英雄とはそうしたものだ。
だがアリの引退後は、明るく、無邪気で、健康的だと作者が強調すればする程、暗い気持になってくる。パーキンソン症候群にかかっていることもあるが、随所にアリの手がふるえたり、いびきをかいて寝てしまうという描写があるからだ。そしてどうもこの本全体に死の影がつきまとう。なかなか生活できるようにならない作者の生活苦も明るい雰囲気にさせないし、作者自身の父の死もこの本の底辺に流れている。どこか日本的な無常観があるのだ。単純にアリの半生を知ろうとしたのに、生きることの哲学的命題を突きつけられて、カウンターパンチを顔面にくらったような気分になってしまった。
「人間が手に入れられるもんなんか、どうだっていいことばかりだ」とアリが言う。富も名誉も栄光もすべて手にした男の口から発せられる。手にした事のない我々はどうすればいいのか。手にしてからそうしたセリフを言ってみたいし、それを悟る時の栄光との落差は辛そうだし、イスラム教徒になってもな〜。
アリきたりの人生もアリかな。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '97年11月号掲載)


