


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| フォトでコラム| 今日もはやく帰りたい|
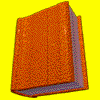 恋愛は幾つになってもしたいもの
恋愛は幾つになってもしたいもの
本屋さんでずっしり重たい本を手にする。「卑弥呼」久世光彦。このくそ暑い時に、邪馬台国の話もないもんだとページをめくる。およよ恋愛小説らしい。しかも主人公の女性は20才の女の子。あわてて本の最後の作者紹介を見る。確か久世さんは結構お歳のはず。一九三五年生まれとある。果たして、人は年齢によって感性は変化するんだろうか。歳をとっても現代のガキンチョの恋愛を描けるものなのか。興味はその一点に絞られた。本の重さをものともせずレジに向かった。
なんと可愛い本だろう。いっきに読んでしまった。可愛いという表現は、なんにでも使える便利で安直な言い回しだと、この本にも書いてあるが、可愛いものは可愛い。「いとおしい」と言えば良いのかも知れない。すべての登場人物を抱きしめてあげたくなる。歳をとろうが若い感性は衰えることはないんだなと、我が身を振り返って安心もした。いや待てよ。この私の感性は20才の女の子より、久世さんの年齢の方に近いから、感じてしまうのかも。これは今の20才の感性を表現できているんだろうか。
待て待て、今の20才の感性など問題ではないじゃないか。一九三五年生まれの感性に触れる事のほうが大事であった。瑞々しさは 今を生きる若者よりも数段磨きがかっかっている。というわけで、これはおじさん必読の恋愛小説である。
久世さんとは一度お会いしたことがある。NHKの「いいもの万来」という自分の愛着のある物を紹介する番組だった。そこで久世さんは古い手動式の蓄音機を持ってきた。かすかに切なく鳴る音が心の琴線に触れるという。確かにどんな陽気な歌も哀しく聞こえてくる。ダンディな趣味人である。私もそうなりたいが、体型がそうさせてくれない。
この小説は、そんな手動式の蓄音機が全編に聞こえてくるようだ。ボリュームの音は小さい。生も死も性も真剣には考えるが、大げさには考えない。大げさに考える一歩手前で止まることがダンディズムなんですな。
恋愛は幾つになってもしたいもの。そんなことを考えながら近くの公園を歩いていると、芝生の上でピタッとくっついたカップルが多い中、一メートルの距離をおいて座っている高校生カップルがいる。今時の高校生にしては珍しい。あの距離を埋めて行くのは女なんだろうか男なんだろうか。女の気持も男の気持も痛い程分かる。ほんのちょっとの勇気。くっついてしまえばそれが自然。分かっているのにできない。始めて手を握る感動。近づけば近づく程、距離が遠くなる事も知ないで。おお〜私の若き感性がほとばしる。感性は不滅だ。でもおじさんはそれを小説にしかできないのか。
なんとも現実は残酷だ。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '97年9月号掲載)


