


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
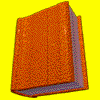 ニューヨークがそうなら東京もそうとう
ニューヨークがそうなら東京もそうとう
子供の頃、多分小学校に入りかけの頃だったと思う。近くの公園に、まだ潰されていない防空壕があり、ロウソクを持って友達二、三人で入っていく遊びがあった。恐くて恐くてたまらないのに入って行く。やっと子供が入れる様な小さな穴もあった。小さな穴より、しっかり立てる大きな穴の方が恐怖感が残っている。大きな穴は誰かいるんじゃないかと足がすくむ。それよりなりより暗闇そのものが恐い、何も認識できない恐怖。その認識が高じてくると、もうこの洞穴から帰れないかも知れないとまで思い始める。多分7、8メートルの距離が、子供には50メートル位の感覚だった。「モグラびと」を読むとそんな子供の頃の恐怖が鮮明に蘇る。
この本は若い女性が実際に地下に潜って、地下生活者のホームレスをルポルタージュしているのでスリル満点、生々しい声が散りばめられている。驚いてしまうのが、大都会ニューヨークの地下に3千から5千人のホームレスが住んでると言う事実。それも只の地下ではない、地下鉄のそのまた下、地下6階くらいの所にもだ。だいたい都市の下がそんなに掘られているというのに驚いてしまうが、ニューヨークがそうなら東京もそうとう掘られているに違いない。そこにはある種快適な空間もあるらしい。工事中の作業員が休憩するための場所とか、もう使われなくなった地下鉄の膨大な広さのトンネル。そこにあるグループはコミュニティを作り、あるいは動物のように潜んでいると言う。一週間も太陽も見ないこともざららしい。ほとんどの地下生活者はドラッグかアル中に侵されている。「三日やったら●●はやめられない」とかいうそんな生やさしいものじゃない。まあそういう人もいるんだが、「地下にいると、人間は動物になる。人間という仮面の下の野生がめざめるんだ。」「路上で犬っころを殺すよりも、ここで人間一人始末するほうが遙かに簡単なんだぜ。殺した後も案外平気でいられる。」「欲しいものがあれば殺せるんだ。殺そうが殺すまいが、たいして変わらないんだ。」どう思います? こういう世界があるという事実。完全に人間やめちゃった人達。いや、やめざるをえなかった人達。地上でガキどもに殴られたり蹴られたりするより、闇に包まれていたほうが、よっぽど安心感があるという人もいる。
文明だ、経済発展だといって、世界が崩壊する時、確実に生き延びるのは地下に住む彼らだとも思うが、今私たちにできることは何だろう。あるホームレスの女性が語っていた。「あなた達は救おうとしなくていいんです。神様じゃないんだから。」私たちのできることは住みかを見つけた人達をそのままに生かしてあげることだけかも知れない。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '97年4月号掲載)


