


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
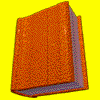 せめて最後はボニーとクライドのように
せめて最後はボニーとクライドのように 新宿、この小説の舞台だが私にとっても青春時代を謳歌した街だ。芝居の稽古が終えれば毎日のように飲み歩いていた。小便横町、今はそんな名称じゃないだろうが東口を出て大きな映画の看板が並んでいる下のガードをくぐった所だ。酔っぱらいがいつも立ち小便をしていた。私もした。新宿ゴールデン街。せまい路地に細い階段、その二階の階段から頭から落っこちた事もある。この小説のように殺伐とした状況でなく、酔っぱらって足を踏み外しただけだ。陽気な転落と言っていい。そして風林会館あたり、このあたりは70年代の当時も変な殺気があって恐かった。すでに無国籍状態になっていたのかもしれない。実際に、歌舞伎町から風林会館あたりは、日本人で土地を持っている人はほとんどいないと言う。
あの時の動物的直感で感ずる恐怖はなんだったろうか。この「不夜城」は快調なテンポで、人間のおぞましさを表現する。やはりあの殺気は、人を人と思わないところから来ているのだろう。人を殺すことを何とも思わない。人がお金に見える。後先を考えずサディスチックに突っ走る。幸いな事に私は、そういう人物に遭遇したことがないから、どうしても人間の暴力に対する怯えが作り出す想像的人物像だと思ってしまう。だがそんなことはないよとこの本は必要に迫ってくる。登人物一人一人がチェスのように有機的に動き、すべての人物が「憎悪と怯え」を持っている。上司が憎いとか、部長に怒られるとかそんな憎悪とか怯えではない、殺すか殺されるかだ。はたして今の時代にそんなことがあるのだろうか。新宿の街の描写が具体的で、日本国籍を持たない登場人物という事もあって、すざましい説得力がある。私は一晩で一気に非日常な時間に酔いしれて読んでしまった。
なによりもこの小説を引っぱるのは男と女の愛の行くえだ。相手を好きなのだが信頼できない。そう書くとよくある恋愛小説のようだが、この信頼できないというのが並じゃない、これまた殺すか殺されるかなのだ。うーむSEXが気持ちよさそう。逃亡と攻撃をくり返す非人間的社会で、恋愛さえオアシスにならない。女が言う「温泉にいこうね」。ああ泣けてくる。これは演歌か。普通ならグァムかサイパンだろう。若いのにこの作家はオジサンの心もくすぐる。映画にしてもおかしくない題材だが、映画だと陳腐になりそう。これは絶対に小説で読むべし。せめて最後はボニーとクライドのようにと祈りながら読んだのに、この作家はなんとも非情だ。でも非情を知らずして情は生まれないのかもしれない。
人が信頼できる、あいつは裏切らないだろうと思える仲間が果たして何人いるか。私は幸福な所にいそうだ。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '96年12月号掲載)


