


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
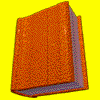 サルから学んだと言うのが
サルから学んだと言うのが
最近、無性にゴリラを長く見ていたいという衝動にかられる。自分が無気力になっているのだろうか。あるいは、人生後半にさしかかり、素朴さへの回帰が始まったのだろうか。こう言っちゃ失礼だが、ゴリラの様子はオーストラリアの原住民アボリジニにそっくり。人類が狩猟民族として生きていた頃の憧れかもしれない。
現実には、ゴリラを見る時間がなかなか取れない。そこで私は素晴らしい方法を見つけた。自分の足をじっと見るのだ。両足より片足がいい。すると、そこにゴリラが出現する。足だけ見ているとどうにも人間に思えない。全くの動物だ。やってみるといい。当たり前のことが強烈な感じで認識されるから。石川啄木の「一握の砂」の“じっと手を見る”は己の動物認識だったのかと思われるぐらいだ。
「舞い上がったサル」的な本は、なんらかのカルチャーショックがないと満足しないものだが、二つ程あった。一つは人間は水棲生活をしていたという説。ちょっと嬉しくなる。、もう一つは、精子の役割。すべての精子が卵子に突進するものとばかり思いたが、精子の中には別の人間の精子が入ってくると、それを防御する奴がいるのだと。人妻と不倫しても子ができにくくなっているらしい。精子はまさに道徳の神様だ。
作者のモリスさんは、人間の遺伝子の98,4パーセントまでがチンパンジーのそれと同じだというところから、人間が動物としての性質を否定するなら、人間は滅亡しかねないと説く。いわゆる進化論なのだが、私としてはこの1,6パーセントの差が決定的の差だと思ってしまうのだ。なぜなら、ゴリラとチンパンジーの遺伝子の差よりも、人間とチンパンジーの差の方が少ないと言う。だが、人間はよりゴリラに似ているのではないか。差の大小ではなく、その質が肝心なことがわかる。その差はどこまで進化を辿っても変わらないじゃないだろうか。
立花隆の「サル学の現在」を読んでみると、一概にサルと言っても、種によって集団維持の様式が全く違うことがわかる。雄、雌の関係、ボス支配の社会、共に分かち合う社会、なわばり認識も全く違う。サル社会はサル社会で進化しているとしか思えない。人間も人間として誕生して、人種によって質のちがう人間社会を形成していったのだろう。サル社会を知れば知るほど、そうとしか思えない。
だからといって、人間が動物であることを否定しようとは思わない。類人猿はきっと先にすんでいたサルから多くのことを学んだんだろう。サルから進化したんじゃなく、サルから学んだと言うのが学者でない私の学説だ。
そう考えると、私がゴリラを見たいと言う願望は、サルからまだ何かを学びたいという、原始的欲求なのかもしれない。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '96年8月号掲載)


