


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
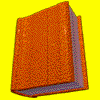 民族意識、それはろくでもないものです
民族意識、それはろくでもないものです もう、目茶苦茶面白い。久々興奮する本を見つけた。映画「月はどっちに出てる」の原作者と帯になかったら、地味なタイトルだけに『夜を賭けて』を私は手に取らなかったかも知れない。1人1人の人物がよく描かれている訳ではないが、そんな事はどうでもいい。小説全体の持つリアリティーと迫力の凄さ。ページが終りに近づくにつれ「もっと、もっと行かせて、まだまだ興奮できる」と心の内で叫んでいた。
全体を流れるのは、戦後まもなくの在日朝鮮人と警察官の攻防なのだが、教科書ではもちろん、日本の大人も教えない歴史がダイナミックに蘇り、今につながって来る。
私は千葉県市川市の国府台に育ったのだが、家の近くに在日朝鮮人の居住区があった。小学生の頃、そこに住む親しい友人が数人いたが、なんであんなバラックに住んでるのとは聞いてはいけない事と暗黙の内に分かっていた。彼らも生きるために闘っていたのだ。
ある日、同級生の顔立ちのはっきりした美形の女の子が「祖国に帰るんだ」と学校を去っていった。その時は先生から何の説明もなく「へえ〜そうなんだ」と転校するぐらいにしか考えてなかった。今、歴史が一直線につながった。彼女は2度と帰って来れない北朝鮮に向かったのだ。不安よりも希望をいっぱい抱え、民族意識に燃えて。当時、北朝鮮の内実は夢とか希望とは掛け離れたものだったらしい。幸せに暮しているのだろうか。
もうひとつ、今になってはっきりした事がある。小学校5、6年だったと思う。私はバラックに住む友人達と野球チームを作っていた。ユニホームもない雑草チームだ。リトルリーグに所属する全員がユニホームを揃えたボンボンチームと対戦した時だ。守っている我々にヤジが飛んだ「チョーセン、ゴーホーム!」。その言葉を聞いた途端、野球は中断、殴りあいの喧嘩になった。私には何が何だか分からず、ただただ呆然としていた。日本でも朝鮮民族は北か南かで争っていたのだ。在日の友人は子供心に大人達の苛立ちを肌で感じ、その節操のないヤジに「てめえらに何がわかるんだ」悔しさではち切れてしまったのだろう。私は呆然としながらもチームメイトを応援していた。
だいたい、民族意識ってなんだろう。子供電話室に相談してみたい。日本人、韓国人、ドイツ人、ユダヤ人。ただそこに生まれただけなのに、人間はどうしてそうした認識を持つのだろう。憎悪は遺伝ではない筈だ。子供のようになってしまったが、私が電話室の先生ならはっきり答えよう。
「民族意識、それはろくでもないものです」と。
ともかく、この本は私の今年のベストワンの推薦。「人はパンのみで生きるに非ず」そんな言葉が空しく響く。( 協力 / 桃園書房・小説CULB '96年11月号掲載)


