


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
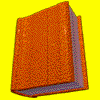 松食い虫に食われる松だ
松食い虫に食われる松だ 人間は必ず死ぬ事は分かっている。なのに、どうしてリアリティがないのだろうか。
病気になると、その恐怖は突然やって来る。ところが治ってしまえば、死は身近な所から遠く離れた、ただの概念になってしまう。身内や他人の死は地上から消えたという妙なリアリティがあるが、恐怖の実感がなく、死を自分の事としてとらえられない。私は馬鹿なのだろうか。
なぜ、死にリアリティがないのか。私は分かった。それは、人それぞれ死に方が違うからなのだ。もし、全人類が老衰で死ぬとなれば、他人の死は自分の死として、確実に認識できるんではないだろうか。ところが、人は突然死ぬ。交通事故、ガン、エイズ、戦争。自分はどの死に方をするのだろう。どの死に方も自分とは違うような気がする。その気持ちがリアリティの欠如になっているのだ。
いや、違うな。私は死のリアリティを持ちたくないのだ。死ぬと分かって、何もやることがないと分かった時、その情け無さは極致に達するに違いない。何のために生きて来たのか、死を自前にして「温泉に行きたい」では可哀相過ぎる。だから私は死を予告して欲しくない、リアリティのないまま死にたい。ウ〜ムこれが本音だな。
畜生、なぜこんなにも情け無い自分を自覚しなければいけないんだ。この『ホット・ゾーン』がいけない。否応なく死について考えさせる。エイズよりも恐ろしい、空気感染するかもしれないウイルスが地球上に存在し、人類絶滅の危機と煽る。「これはノンフィクションである」と始めに断ってあるのでそうなのだろう。その死に方が壮絶だ。この本では「炸裂」という言葉を使う。穴という穴から血を流し、目、鼻、乳首からさえ、血とともにウイルスが飛び出して来る。人間が内側から食われるのだ。いやだよ、勘弁してくれ。
そんな空気感染するウイルスをどうやって防げばいいんだ。この作者はなぜ黙っていることができないんだ。知ってどうなる。バカタレ!誰かこれは映画の脚本だと言ってくれ!
しかし、人類にはいろんな人がいる。そのウイルスと感染する事を恐れず立ち向かう医学者がいるという事実だ。私にはウイルス好きとしか思えない。私と正反対にいる人種だ。こういう人は死に直面しても温泉に行きたいなんて言わないんだろうな。「やり残した事がある。人類を救うのは私だ。このウイルスの殺戮の全貌を知りたい、無念だ」パタッといくんだろうな。
本当に生きるって何でしょう。私は決めた。松食い虫に食われる松だと思う事に。
今、松も内から虫に食われ、パタパタと倒れている。松は自分の死を知っているんだろうか。なまじ知恵があるからいけない。こんな本読むんじゃなかった。私は松だ。( 協力 / 桃園書房・小説CULB '95年6月号掲載)


