


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
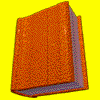 ほとほと頭のいい人
ほとほと頭のいい人 記憶とは不思議なもので、全く忘れているような事が、ある瞬間に、ある言葉で猛スピードに逆戻りして、遥か遠くの時代に連れて行く。
この『幻想薔薇都市』の著者、加藤周一さんの名を書店で見た瞬間、大学に入学したての教室、回りにいた友達、劇研の部室、その頃好きになった女の顔、膨大な記憶が蘇ってきた。もう25年以上も前の事だ。
最初の授業で、サリンジャーを訳している野崎先生が、「加藤周一さんは日本のインテリジェンスを持っている唯一の人だ『羊の歌』を読むといい」とおっしゃった。まだまだシニカルなおじさんでなかった純情な私は薦められるままに読んだ事は覚えているが、その内容は全く覚えていない。それ程私に影響を与えなかったのだろう。いや、急に無口になった時期と重なるから、その本の内容と関係していたのかも知れない。それにしても、加藤周一という名が、脳に引っ掛かっていたとは……。
そしてその名がイモヅル式に過去の記憶をひきずりだしタイムスリップさせてくれたのだ。なんともおかしな体験だった。
そんな訳でこの本も学生に戻った様な気分で読みはじめた。13の短編が入っているのだが、異国の地という共通項はあるものの、でたらめともいえる構成で、脳味噌をぐらぐら揺すられた様な気分になる。恋愛至上主義とも思える情緒的でロマンチックな文章があるとおもえば、論理的である事を遊ぶパロディーがあり、エロチックな文章あリ、芸術論あり、未来都市の認識論ありで、最後尾を走るマラソンランナーの如くついていくのがやっとだ。ほとほと頭のいい人だ。
「気の集散(天地の気、集まって人が生じ、散じて人が死ぬ)を以て生死を説くのは、『気』を定量化して『エネルギー』とし、天地を定量化して『四次元空間』とみなせば、ほとんど今日の常識となります」。ねえ、ちょいと分かります? どこが常識なんだろう。かと思えば、過去の恋愛を振り返り「何故生きているか、を問わなかったときに、ぼくは生きていたのです」とか言ってしまうのだ。こちらは分かるが、加藤氏の脳の中がまるでわからない。
理解不能の文章との出会い、それはそれで、理解不能の笑いが何故か面白い様に、楽しい事でもあるのだが、俺の頭が、思想、哲学に向いていない事を改めて認識してしまった。そういえば、学生時代読んだ哲学書は、ファッションで読んではいたが、ほとんど理解できなかったもんなあ。それでも分かったふりして、ダイジェスト版で理解してさ。ああ、嫌だ嫌だ。まだまだ、学生時代が蘇る。女に振られて、ビンタされて、若かったあの頃、何も怖くなかっただってさ。
政治家よ、人間の脳の差別をなんとかしろ!( 協力 / 桃園書房・小説CULB '94年12月号掲載)


