


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
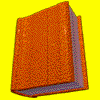 悟りを開くには
悟りを開くには
らもさんと久しぶりに会ったのは、『ガダラの豚』が推理作家協会賞の連絡を受けた次の日だった。「へえ〜、あれが推理小説なのか」と自ら言う。なんとも無頓着な男である。その一言でガゼン読む気になった。作家が推理小説と思わない推理小説。面白そうである。読んでみた。確かに推理小説とは言い難い。謎解きがないのである。後半はダイハードさながらに、はちゃめちゃになってはちゃめちゃのまま終わってしまう。推理の余地はない。らもさんが信じる事を読者も信じる、それだけだ。けして無理強いはしない。
らもさんと会ったのは、大阪発のグルメ番組。彼が作家、私が編集者という設定で食べたり釣りをしたりと、のらりくらりとしていればいい番組だった。一緒に歩くと、およそ権威から掛け離れた人なのに、どんどん昭和天皇に見えて来る。歩き方がそっくりなのだ。よちよちと1歩1歩確かめる様に歩く。らもさんを走らせてみたいと何度思ったことか。あの歩き方では確実に転ぶであろう。足は脳味噌を運ぶ道具のようだ。だからであろうか、走れないらもさんは実に暝想が似合う。4、5人で話していても、キチンと座ってグロテスクな笑みを浮かべ、黙って他人の話を聞いている。明らかに何も考えていないとわかる。それを他人にわからせるのだから、これはもう暝想の達人である。
この本にもそこはかとなくおかしい阿闍梨様や教祖様、呪術師がゾロゾロ出てくる。その風体、物腰が、らもさんとだぶって、私は楽しくてしょうがなかった。
実はこの本、本屋で一度手にして、余りの重さに棚にそのまま返した事がある。らもさんの友達は読まない理由として、寝っころがって本を上に手で支えて読む習慣があり、この本だとウトウトすると顔面に大怪我をする恐れがあるからだと言っていた。読んでみればその心配は御無用。あの厚さなのに眠気をもよおす所がない。ストーリーの展開もさることながら、ろくでもない無用な知識が出てくるわ、出てくるわ、説得力がありそうでなさそうで、笑うしかないのだ。
圧巻はアフリカに行くくだり、ワクワクしてしまった。いったいどんな本を読んで無用の知識を得ているのか参考文献を見てみれば、「エチオピアにおける寄生虫病とその背景」「毒の文化史」「呪術」やら「月刊少林寺拳法」まで、普通の人には全く無用な本をごまんと読んでらっしゃる。私は悟った。悟りを開くには、身になるものではダメ、無用の用を知る事ではないかと。
私はらもさんに聞いてみた「文学とはなんですかね」と。彼は得意満面な顔をして、つい今しがた悟りを開いたように「スジやね」と答えた。なんとも含蓄のあるお言葉ではないか。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '94年9月号掲載)


