


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
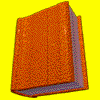 だから大人は無意識に
だから大人は無意識に
著者はあとがきで言っている。「ぼくたちは誰でも子供であった。その子供は消えてしまったのだろうか。ぼくにはそうは思えない。大人のなかに『内なる子供』が眠っているはずだと思う。もしそんなことはないと言われると、とまどうどころかひどく不安だ。子供であった自分と大人になった自分とが全く別人だとすると、ぼくはいったい何者なのか」。引用が長くなった。この『子供誌』が子供にまつわる書物の引用が多いので、すぐ影響されてしまう。あとがきを読んで本を選ぶことはよくあるが、この本がまさに先の引用した部分に引かれて読む気になった本。著者とは反対に、「内なる子供」を探す旅ではなく、子供だらけの俺の、大人の部分を探ろうとしてだ。はたして、大人と子供の違いは何なんだろう。
先日、40を過ぎた野郎4人でキャンプに出かけた。気分はスタンバイ・ミーである。テントに寝て溪流釣りをしようという計画。ところがひとり大人がいて、万が一夜が寒かった場合のため、近くに温泉付きの安宿を用意したというのだ。なんていう事だ。森に抱かれて、森と一緒に朝を起きてこそキャンプではないか。寒さがなんだと、その大人を皆でなじった。夜になり、まあ、どうせだから温泉だけつかりに行こうという事になった。宿に入れば、テントに戻ろうと言い出す者は誰もいなかった事は言うまでもない。「内なる大人」を確認してしまった。代替案を用意するなど子供にはできない。大人は偉いのだ。だが、次の日俺は、せめてもの抵抗として、子供の頃の押し入れ閉鎖空間の快適さが忘れられず、ひとりテントで昼寝を敢行した。全く俺は子供なんだか大人なんだか。
この本では子供に関していろいろ言及しているが、なかでもユートピア1世代論は力が入っている。親は親、子は子という基本的考え方に立てば、どんな理想も次の世代では管理的になり、反吐が出ると言う。子供に深い愛がなければ言えないセリフだ。
また大人になって忘れてしまう事の一つに、子供の頃の死に対する強い恐怖があると言う。言われてみれば鮮明に思い出す。幼児期に、昼寝から目が覚めて、母が買い物に出かけていない。天井の板模様が動いているように見える。死ぬかも知れないと思った。母が帰って来て泣き叫んだ。母には説明はしなかった。母は淋しかったのだろうぐらいにしか思っていなかったろう。あれは確かに死の恐怖だった。だからなんだと言われても困るが、今もあの時の感情を覚えているとは、記憶力の悪い俺にとってすごい事なのだ。
そして思う。あの恐怖の中で死んでしまうのは嫌だ。だから大人は無意識に安宿を選んでしまうのだろうと。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '93年7月号掲載)


