


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
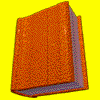 大人の童話
大人の童話
「この本は面白いよ」と他人に言われても、なかなか読む気にならないものだが、同じ日に、全く別の人から同じ本を勧められると、ムム、どんな本なんだろう。この口コミを止めるも、蔓延させるも、オレ次第だなという気になってくる。
この『悪童日記』は、作者が女性という事もあってか、口コミは女性の方から流れて来ている。シティボーイズライブの稽古で、あの大竹が稽古もせずに、ひたすら本を読んでいる。もともと、我々の稽古は無駄話が8割で、ダラダラ時間が流れていって解散といった余程厳しさに欠けたものだが、話に加わらない大竹も珍しい。「なんの本だ」と聞けば、「いや、女房に勧められてね、なんだかわからんが、面白いんだよ。」と言う。そして、我が家に婦ってみると、その本がテーブルに置いてあった。「どうしたんだ」と妻に聞けば、友達が読んでみろと置いていったという。なんとも恐ろしい偶然。どうしても読めといっているようだ。まさか、大竹の女房が何10冊も買いあさってばらまいているとは思えない。確かに、なんだかわからない面白さがある。意味がわからないという事でなく、説明しづらい面白さなのだ。感動がある訳ではないが、妙なすがすがしさがある。ハンガリーの戦時下という悲惨な状況でありながらも、悲しみは湧いて来ない。内容は奇想天外な要素が含まれているので、これから読む読者のためにも語らずにおく。
文章が感情を書かず、事実のみを書くといった手法をとっているので、つっかえる事なくスイスイと読めてしまう。大人の童話といったところか。愛のある非情さが、全編に流れている。双子の少年が主人公なのだが、この2人は大人になってゴルゴ13になってもおかしくない。非情である事が、実は深い愛であったりする事はよくある。情けは人のためならずだ。確かに、情を施すのはたやすいが、行動に移すのは難しい。行動に移せば自分の身も危うくなるからだ。情けをかける代わりに、その人を殺してしまえば、その人は悲しみから救われる。だが、論理は大きく飛躍している。でも、何だかすっきりする。そうした単純な残酷がこの本にある。
情の最たるものが、男女間の営みであろうが、これもまた情なしで、欲という事実をタンタンと書かれると意外と興奮する。「行かせて!」と言われて、そのまま天国に行かせてあげたら、これまた論理は飛躍しているがすっきりする。まあ、これは本とはまるで関係ない話であるのだが……。
こうした本が女性達に読まれていることも、現実欲求不満の女性心理の一面が覗けて背筋がゾクッとするものがある。ダメな人間はダメと言いきる力は女性の方にこそあるのかも知れない。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '93年4月号掲載)


