


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
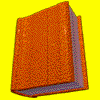 脳を愛するのではなく、人を愛す
脳を愛するのではなく、人を愛す
オリンピックの見すぎで、涙腺がオバサン化してしまった。この涙という奴は全身にシャワーを浴びたような心地良さがあるもんだから、ついつい癖になる。まあ、これを専門用語ではカタルシスと言うのだが、年をとるにつれ涙に対する抑制がきかなくなる。情けないと思いつつ、泣きたいという欲望に身をまかせてしまう。そこには理性のかけらもない。
学生の頃、テレビを見て泣いているお袋に「なんで、こんな所でなくんだろう」と不可思議に思ったが、自分の身にふりかかってきている訳だ。脳の働きのどこかが弱ってきているとしかいいようがない。だが、弱った所で泣く事は気持ちがいいんだから。そんな脳など弱ってしまえと開き直ることにした。だから私の場合、オリンピックの金メダルがかかった試合など、日本ガンバレ、勝つんだという声援でなく、「頼む、オレを泣かせろ!」と叫んでいる。銀はダメ、金の涙こそ具体的で、別のなんの要素もなくて泣ける。山頂を登りつめたカタルシスだ。しかし、その山登りを選手と共有するためには、長い時間その競技を見る必要がある。時間と涙の量は正比例する。マラソンであれ、柔道であれ、同タイムで見て感動があるというものだ。
しかし、やっと本題に入るが、この「妻を帽子とまちがえた男」に出てくる神経に障害を持った数多くの人物の1人は、これができない。2分前に起こった出来事をどんどん忘れて行く。脳の記憶装置が故障している。他はすべて正常なのに、記憶が30年前で止まって、他の記憶を受け付けないのだ。実際の患者さんの話なので、明日は我が身といったリアリティが迫ってくる。この人の場合、2分間泣き続ければ、今自分が何に泣いているのかさえ分らなくなる。永遠の短距離選手、まさにアイデンティティの崩壊だ。また別の人物は、自分の左足が自分の物でないと主張する。この小さな脳のどの部分を触ればそうなってしまうのだろうか。まさに、脳が自分の足だと決定している事がまざまざとわかる。またある人は、脳で自分の足だと認識できても、それを自然に動かす脳神経が侵され、視覚でそれをやっている。目をつぶると自分の物でなくなってしまうのだ。視覚でバランスをとって歩行し、物を掴むのだ。この位置に足があれば倒れないといつも目で確認しなければ、立つという行為はありえない。脳とはなんと入り組んだコンピューターなんだろう。他にも信じられないような患者が次々に登場する。
この本は、人間が人間たらしめているのは何か、根源的なところで考えさせ、教えてくれる。そして、脳を愛するのでなく、人を愛すのだという事も。息子が大きくなったら読ませたい本の一つとして、とっておく事にした。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '92年10月号掲載)


