


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
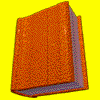 飲んで正常、飲まなければ異常
飲んで正常、飲まなければ異常
シティ・ボーイズのライブが1週間あって、公演後は連日の酒びたり。どうも頭がボンヤリしている。ライブはお祭りのようなもので、酒のないお祭りなど考えられない。ところがどっこい、メンバーの大竹と斉木は酒を1滴も飲まない。「酒の味がわからないとはかわいそうに」と私が言えば、斉木は「じゃ、お前はコーヒーの味がわかるのか」と怒りだす。ちょっとその怒りは違うような気がするが、彼も飲めるものなら飲みたいと思っているのを知っているので、それ以上は追及はしない。自分はお酒に合う体質でよかったとつくづく思うだけだ。
しかし、この「アル中地獄」を読んだ後の2、3日はお酒が気持ち良く喉を通らないのにはまいった。とんでもない本を読んでしまった。夕方に飲む1杯のビールが昼と夜の時間を明確にし、2つの人生を生きている気にさせるお酒。それがなかったら、生きている意味の半分はないと思っている私に酒をまずくさせるとは、まったく読むんじゃなかった。
お酒を飲むのが非日常的な精神的昂揚と狂気に接近できるのに、アル中患者はその逆で、酒を飲んで正常、飲まなければ異常では、まったく何のための酒かわからない。飲まない事を楽しむようになるのかしら。オイオイ、ふざけている場合じゃない。アル中の禁断症状はもの凄いものがあるのだ。前々から、アルコール依存症の人にとってテレビで流れるビールのCMは地獄のように苦しく、周りの人をハラハラさせるとは知っていたが、あれは毎日が拷問というより、生涯の拷問になるとは、怖いですよ。お酒がドラッグである事を再認識させられました。
この本、帯に「日本一のアル中男」とあり、どこかとぼけた感じがする。きっと笑わせてくれるだろうと買ったわけだが、確かに、他人の狂気は面白い。精神病棟での禁断症状の幻覚は圧巻だ。自分の脳が爆発して、床一面に砕け散るのが見えるのだという。回りの患者に協力してもらい、1つ1つの脳細胞を丁寧に拾い集め、もとの頭蓋骨に収めてほっとした瞬間、また、爆発しちゃうのだ。これには、ちょっと悪いと思ったが大いに笑わせてもらった。回りの患者達には見えていない、床に散らばった脳細胞。それを見えている様に拾ってあげるなど、なんと心優しき人々だ。それに、完成した途端また爆発しちゃうとは、予測のつかない秀逸なオチではないか。他にも、幻聴やら酒の入手の仕方。当人には悲惨で、他人には切なくおかしい話が続く。
結論としては、私はお酒をやめようとは思わない。だが、お酒という人類が生みだした偉大な文化に感謝を忘れず、お酒を決して精神的支えや道具として使わないよう胆に銘じた。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '92年7月号掲載)


