


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
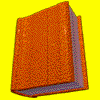 この本を二度読んだ
この本を二度読んだ
私程、眠りに対して無抵抗な人間はいないかも知れない。何しろすぐ寝る。本を読んでいても、テレビを見ていても、睡魔が襲ってくればすぐに命を預けてしまう。映画館の暗がりにも、滅法弱い。一度も眠らずに映画を観終える事は滅多にない。あまりに情けないので、自分の腿をつねったりするが、痛い。痛さと眠りのどっちをとるのだお前は?と自問自答しているうちにスンナリ寝ている。ボートで漂流すれば、私は真っ先に死ぬタイプである。
そして、その一方で、眠る事を極端に嫌う人もいる。情報大好き人間に多い。英語ペラペラの小林克也さんもその1人。生きているのに、眠るなどもったいない、一時でも情報を得ていないとイライラするのだと言う。私に言わせれば、生きていて、眠りの快感知らないなんて、それこそ生きている意味がないと思ってしまうのだが……。
まあ、いろんな人間がいて世の中は面白い。とかなんとか、世界で一番つまらない結論をだしたところで、この本「眠り島」だ。タイトルだけみれば、誰しもが思う。暇を見つけてはヤシの木陰で眠りほうける島の話かと。とんでもない間違いである。なんと私はこの本を2度読んだ。滅多にある事ではない。1度目は睡魔とお友達になりながら、何度も中断して気がむいた時に。そして、2度目は一気に。なんと言おうか、この本は自分の脳の中を散歩するような妙な心地良さがある。前にここで書いた「やし酒飲み」の奇想天外さがあり、ち密な計算がある。書き始めている内にああこんなことになっちゃったといった小説ではないのだ。頭脳明晰、したたかおじさんである。
そもそもこの島は五万人の昏睡患者、つまり植物人間が収容された島なのだが、この患者達は目覚めていた時より、何倍も生き続けている。そこに1人の男がある人を調査しに送りこまれるという話。最後に近未来を暗示する恐ろしい論理が展開される事になる。昔、私らがやった医者コントで、婦長が看護婦に「植物人間の小林さんに、肥やしをまいたのは誰?」といった人間性を疑われるような物があったが、そんな直接的な笑いでなく、全編に乾いた別役風笑いが散りばめられているのだ。なにしろ、その調査員はキリンをつれて島に入っていくのだ。オイオイ、どうしてキリンなの。それだけで笑ってしまう。何度読みかえしても、文章が映像化されない。それがどうも、グニュグニョと脳を散歩している様な気にさせるのかも知れない。そして、この島は時間も空間もずれているというのだ。実にわかりやすく、不思機な体験ができる。それは現実の世界でジェットコースターに乗るよりも、よっぽど面白い。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '92年5月号掲載)


