


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
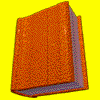 アンニュイとメランコリーのごった煮
アンニュイとメランコリーのごった煮
電車の中で本を読むのは、外界に薄い幕を張って、公然とオナニーをする様な感覚があって、妙に、本の中に没頭できる。そして、他人が、どんな本を読んでいるのかを、薄い幕を破って覗き見するのも、なかなかスリリングなものがある。
私の隣に座っていた18歳ぐらいの娘さん、美形とは言えないが、ポッチャリとしていた。夢中で文庫本を読んでいる。チラリと見れば、なんと、「人間失格」ではありませんか。今どき、太宰治を! まあ、もともと、うら若き乙女が読むような本であるのですが、けなげに読む姿は、現代にマッチしておらず、その落差にオジサンはニヤリとしてしまった。なんとなくその女性の精神構造がよめそうで、ひょっとしたら、くどけるかも知れないぞとか思ってしまう。
そして、その日、仕事先で、イケイケギャルの1人が文庫を買ってきたという。それが高村光太郎の「智恵子抄」だって。なんだか、タイムスリップした様な一日だった。
マスコミがとりあげる、お金持ちでカッコよく遊ぶ若者といったイメージとかけ離れた、もう一つの現代を生きる連中も、確実にいるという事だろうか。情報の多様化と一緒にギャルの多様化も進んでいるのかしら。
そして、今回読んだのが、そんな、もう一つの青春を生きる本。日本の伝統的な純文学的私小説というか、ド暗い! 「ア・ルース・ボーイ」、題名から受けるイメージは、怠け者の本かいな、こりゃ気楽に読めるぞといった感じだったが、読み終えた日は、アンニュイとメランコリーのごった煮になってしまった。主人公の18歳の高校生が、学校をやめる。まあ、これはよくある事。しかし、新聞配達をやっている様な、根に真面目さがあるだけに、暗さがつきまとう。そして、元同級生だった女性と同棲を始める。なんじゃ明るいじゃないかとお思いでしょうが、その女性に生後1ヵ月の赤ちゃんがいて、しかも他人の子。そして、なんと3畳の部屋でのアパートぐらし、今時、3畳。暗さに拍車をかけるのが、主人公の少年期。母親の愛情薄く、知らないおじさんに性的な暴行までうけちゃっているのだ。いたれりつくせりの暗さ。それを、私小説の語りで、淡々と書くもんだから、強烈な説得力がある。ガンバッテ生きろよとしか言い様がない。まさに、1人1人に人生があるんだなと思ってしまう。
私も、巷暙ちまた暠に「神田川」が流れていた頃、今の妻と同棲した口だが、倦怠とかだらしなさを妙に楽しんでいた。それは全く生活感がないものだったが、この主人公の様に18にして生活感を持つとは、今でも責任感のない私には、衝撃的な事であった。そして、次の日には、この小説の事は忘れてる、なんとも、私は幸せな人間なんだろうか。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '91年12月号掲載)


