


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| フォトでコラム| 今日もはやく帰りたい|
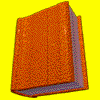 頼むから、この本の作者は女性でありますように
頼むから、この本の作者は女性でありますように
「脳病院へまゐります」。なんというタイトルだろう。脳病院は誰かに行かされるのが本来だが。このタイトルには自ら行く意思がある。それに「まゐります」ときた。「い」が「ゐ」である。時代が違う。虚構性もたっぷり味わえそうと、タイトルにちょっとした笑いを堪えつつ、すぐに本屋のレジにむかった。
作者の若合春侑さんとは男なんだろうか女なんだろうか?読み終えた後もわからない。誰かに聞けばすぐわかることなんでしょうが、女性であることを願いつつそのままにしておく。猛烈に女性であって欲しいと思う。なぜか、女性言葉で手紙のように綴られた文体ということもあるが、その内容がそう思わせる。男性作者ならエロ小説になりそうだが、女性なら騙されたという感覚もなく、心から女性の性的な深淵に触れた思いがする。
性的虐待を受け、辱められても、好きでたまらないからされるがまま、会えなければ会いたくなる。男の強さと女の弱さ。サディスッチクな変体プレイがエスカレートしていくのだが、エロスよりもなぜか女性特有の性(さが)が変な快感となって刺激してくる。好きという感情は自らの勝手な思い込みで作りあげられていくものだが、脳病院までいくほどに惚れる。その非日常性はドロドロしてるんですが、妙な爽快感があります。
「前略、貴方様の云う通りに致したう存じます」そういって注連縄やら潅腸、グリセリンなどなど、自ら用意する女性。男性は命ずるだけ。それがやさしさに見えてくる。こんなことってあるんだろうか。男性がこつこつ用意しない所がエッチで虐待ですね。明治ですね。谷崎順一郎の「春琴抄」が出版されたのが同時代という設定で、「春琴抄」にも触れているんですが、青春期に読んだ衝撃的なエロスの感覚も思い出しました。人に惚れるとは、性の快楽をむさぼるより、惚れるという行為そのものが異常なんですね。
この本にはもうひとつ「カタカナ三十九字の遺書」も収められているんですが、もう一気にいけますね。夏にホラー映画を見るより涼しくなれます。主人に仕える女中。閉鎖された空間。女性が待つだけの営み。恐いです。この本に時代を越えた普遍性があるのかと自問自答してみたんですが、女性の構造的に受身の肉体であることを考える時、深い深いところに真実があるような気がしました。「ワタスハバカニナリマスタ」こんな書き出しから始まる遺書。「脳病院へまゐります」と似た滑稽さがあります。
時代に守られて強い女性が多い今の時代、忍耐を経て自立に至る女性の強さは男性に計り知れない強い意思があるような気がします。
頼むから、この本の作者は女性でありますように。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '99年9月号掲載)


