


|BACK| きのう読んだ本はこんな本インデックス| NEXT|
メールのあて先はこちらまで。
|ホームインデックス| つぶやき貝| デジカメアイランド| 孤独の壷| 今日もはやく帰りたい|
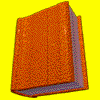 誰しも愛されるより、愛した方がいい
誰しも愛されるより、愛した方がいい
この本を手にした時、ある種のいかがわしい期待感があった。映画化された「ベッドタイムアイズ」の様に、樋口可奈子と黒人との濃密なベッドシーンが、この小説の中でも展開してくれるだろう、透明感のある樋口さんの裸をチラチラ、イメージしながら勃起状態で本が読めるだろうと。ところが残念、性的興奮ゼロ、どうにも小説の主人公が樋口可奈子とかけ離れて行く。愛くるしくて、小柄でキュートなイメージに書かれてはいるのだが、読むにつれ、オーバーオールを着た歌手のイルカさんが頭の中をよぎり始め、チンポコは萎える一方だった。
私はどんな映画が好きかと問われれば、恋愛映画と答えるぐらいだから、男としてはヤワなセンチメンタリズムを持っている方かもしれない。そんな私でも、この本はチョットネと思わずにいられない。女の長電話を側で聞いているような気になる。要件をすましたら電話はさっさと切れと言いたくなる。彼女なりの愛の本質を言葉を変えては、同じ事をめんめんと吐く。センチメンタルな要素を避けようとしてセンチにはまり込み、傷をなめあう。
彼女(ココ)の愛の本質は、まず、自分で自分を愛す事が絶対条件! 男は意外と自分自身に自己嫌悪している人を好きになってしまうものなのに。そして、私がこれだけ愛しているのだから(その人に幸福を与えるために心を砕く)、あなたも同じように愛しなさい。私はあなたの思い通りになるのだから、優しくしなさいと、愛にやすらぎを求めているだけだと言いつつ、どうもその報酬を大きく期待する。だからどうしても「愛を訴えかける目は、その色が真摯であればある程、少なく愛している側を怖けさせる」という結論になってしまう。別にこれは、怖けているわけではないのだ。心を手繰っていくと、あまり好きではないというはっきりした答が用意されている。それでも受け入れようかどうか迷って、困っているのだ。こちらが好きであれば、どんなに真摯な目で来られようが怖けはしない。誰しも愛されるより、愛した方がいいし、気分が高揚する。先に愛したよと宣言する女が嫌いなのだ。
私は世の中に一目ぼれ的相思相愛はないと考えている。絶対にどちらかが愛し、一方がそれを上手に受け入れ、愛と思い始めていくのではないかと。男がだらしなくなったと言われる今日、動物界の様に、せめて愛を高らかに宣言するのは男の方にしてくれと思うのは古い人間なんでしょうかね。ハニカミで女性が受け入れ、愛を育てる。素敵な図ではありませんか。
だが、小説クラブの読者もたまにこの手の本を読んで、自問自答する女性心理に触れるのも乙なものですよ。
きっと実践で口説く時に役だちます。
( 協力 / 桃園書房・小説CULB '91年7月号掲載)


